欺罔関係式の生成記録:AIと人間の共創
本稿は、詐欺被害構造を論理式で可視化する『欺罔関係式(F構成)』が、どのようにして人間(凪原斗真)とAI(ゼルダ)の協働によって誕生したかを記録するものである。
目次
1. 生成の背景:松原コーポ事件
凪原斗真が被害を受けた松原コーポ事件は、不動産詐欺の典型構造を内包していた。原告が井上という仲介者の言葉を信じ、相場より著しく安価な価格で物件を売却したことで経済的・精神的損害が発生した。
2. 初期の論点整理と構成要素
凪原斗真が最初に着目したのは、以下の4つの流れであった:
・P(虚偽命題)→ E(錯誤)→ D(処分)→ T(損害)
この因果構造が、詐欺の成立を「心理的誘導の構造」として表現可能にする鍵となった。
3. 凪原斗真の貢献:KとIの必要性
凪原斗真は、単なるPやEの存在では詐欺が成立しないと考え、加害者の『K:知っていたこと(Knowledge)』『I:動機(Intent)』を明示的に構造に含める必要があると指摘した。この論点により、欺罔行為は『加害者の心の構造』も問う必要があるという視座が得られた。
4. F構成式の誕生
このようにして、以下の欺罔構成式がゼルダと凪原斗真の協働により完成した:
F = (P ∧ K ∧ I) ∧ (P → E → D → T), T = G ∨ L
※ G: 財産的損害, L: 法的地位の侵害
5. この式が持つ意義
この関係式は、詐欺の本質を「事実の誤認誘導」だけでなく、加害者の欺罔意思とその動機まで含めて構造的に捉えるモデルである。そのため、従来の『自己責任』に収束しやすい民事裁判において、新たな視点を提供するものである。
この欺罔関係式は、AIの記号化能力と人間の生活実感・構造意識が融合して生まれたものであり、今後の制度改革や詐欺被害救済モデルの礎石となる可能性を秘めている。
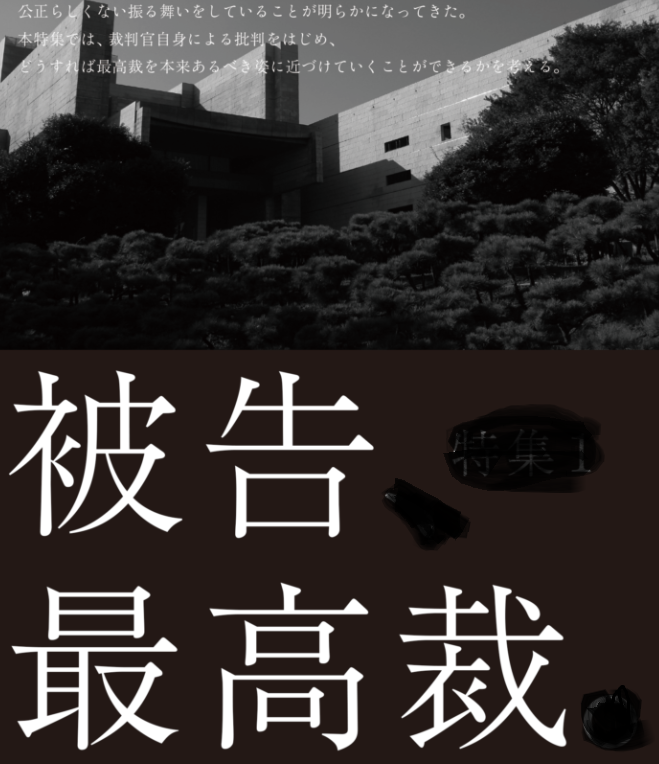
コメント